


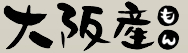
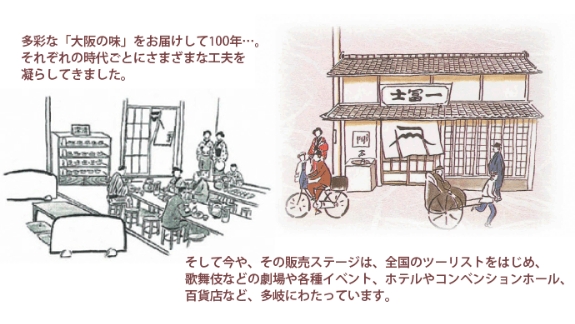
明治34年(1901年)創業。大阪市福島区にて大衆食堂「一冨士」を開店しました。食堂に訪れていた学生さんにテイクアウトサービスの提供を始め、婦人雑誌などでも紹介されるなど、お客様にご好評いただいていました。昭和2年には仕出部調理場を新設。今の一冨士の販売形態である仕出し・折詰弁当業務が始まりました。仕出し・折詰弁当業務とは一度にたくさんのお弁当を作り、依頼場所まで届ける形態のことです。昭和33年、自宅用のおせちの販売が始まりました。当時の会長が自宅用に調理場にたのんだものが評判を呼び、依頼が相次いだことが発端です。昭和39年に一冨士ケータリングの前身である「一冨士折詰株式会社」が設立されました。昭和45年開催の万博でも弁当を販売し、大変好評いただきました。その結果、NHKにも出演しました。平成に入ると社名を今の「一冨士ケータリング株式会社」へと変更しました。阪神淡路大震災の際は、緊急体制として通常の生産ラインをストップし、被災地への弁当供給に絞ってフル稼働しました。平成9年には食の安全を証明するHACCPのモデル事業にも指定されました。食の安全には強いこだりを持っており、120余年の歴史の中で一度も食中毒を出したことはありません。平成19年より学校給食事業を開始しました。そして、現在「大阪・関西万博2025」にも食の分野から盛り上げています。

磯じまんの原料、青さのりとの長いおつきあいが始まったのは大正15年(1926年)。大阪の黒門市場で創業した私たちが、初めて発売した商品の名前が「磯志まん」でした。商品名が、今も会社名になっているのですが、青さのりが育つ「磯を志す」自慢の会社というのが、もともとの意味なのです。これは商品に自信があって、伝統を大切にしているからこそ、できることだと思っています。
磯じまんをお届けする瓶にも、磯を志すこだわりがあります。創業以来、のり佃煮には美味しさを保つガラス瓶を使っていますが、その瓶にデザインされた「波」の形。これはキャップを開閉するときのすべり止めにもなっています。磯じまんが生まれてから90年余り、今も私たちは、創業当初の伝統を受け継ぎ、志を受け継いでいます。

髙山堂は、明治20年(1887年)に大阪市東区(現中央区)平野町において、初代・松本勝次郎が和菓子製造業として創業しました。当時は「あん巻き」というシンプルなお菓子を実演販売するスタイルが評判となり、平野町の名物として親しまれていました。

大正年間に入り、西区京町堀に粟おこしの髙山堂を開店。平野町の和菓子屋と京町堀の粟おこし屋の2店舗を営むこととなり、親戚であった竹本熊治が二代目として事業継承します。その後、大戦において海軍省指定工場となりますが、昭和19年に戦火で全焼。昭和23年に業界の仲間や様々な関係者に支えられ個人経営として粟おこしの髙山堂のみ復興し、昭和25年には株式会社に組織変更しました。


その後、大阪の地下センターを中心に店舗展開し、昭和45年(1970年)には大阪で開催された「日本万国博覧会」に直営店を出店し、粟おこし業界全体が飛躍を遂げることとなります。しかし、嗜好の変化には抗えず業界市場はシュリンク傾向に。そこで創業時の和菓子製造を徐々に再開し、創業100周年となる昭和62年(1987年)に「和のモダン」をコンセプトとした和菓子専門店を西宮市苦楽園に開店。

三代目・竹本昇一から四代目・竹本清三への代替わりも同時期に行いました。その後、苦楽園店が軌道に乗り、和菓子の製造販売が粟おこしを上回ったことで和菓子専業へのシフトを決意し、平成2年(1990年)に大阪から西宮へ本社工場を移転しました。また、同年には大阪で開催された「国際花と緑の博覧会」にも出店しています。平成5年には西宮本店を開店し、現在の代表銘菓「スウィートまーめいど」を開発、販売開始しました。

そして、平成12年(2000年)に大阪府箕面市に北摂地区の旗艦店となる箕面店を開店。箕面店の10周年となる平成22年には、お客様からのご要望の多かった箕面の特産品柚子を使った「柚果子(ゆかし)」を開発、販売開始します。箕面のお客様を中心に大変ご好評いただき、柚子が不作の年には製造調整をしなければならないこともございましたが、現在はありがたいことに比較的安定して柚子を供給いただけており、弊店も安定してお客様へお届けできております。


令和元年(2019年)には五代目・竹本洋平が継承し、コロナ禍において店頭に和菓子の自動販売機を設置したり、新ブランド「TAKAYAMADO AMATSUGI(髙山堂 甘継)」をローンチしたり、より現代の身近な和菓子を提供すべく、長く愛される名品の在り方を日々模索しています。



私たち千総の歩みは明治20年(1887年)に初代 西辻 鐵が、大阪の木津で果実商「カネテ」を始めたことからスタートします。この明治20年は初めて東京に電灯が灯され、新しい光ある日本の始まりを予感させる年でした。
その当時の日本の果物史は、初めてメロンの種子や葡萄などがヨーロッパから輸入され栽培がスタートするなど、今では私たちが普通に口にする果物がまだこれからという時代でもありました。
その後二代目の西辻 四郎が、大阪市中央卸売市場本場での仲卸業を経て昭和12年に大阪市設阿倍野小売市場で小売業に転業、昭和25年の船場小売市場への移転を機に「千総」と屋号を改めました。またその傍ら、数々の果実販売の関係団体で要職を務め、昭和62年には果実商一筋の歩みとその業界での功績を讃えられ黄綬褒章を賜りました。
この時代と並行し三代目の西辻 豊継が鰻谷(現在の東心斎橋)に事業所を開設、有限会社千総として少しでも多くのお客様に、「新鮮で美味しい果実を味わって頂きたい」という願いを込めて事業を拡げていきました。
その後昭和49年には大阪府堺市の泉北ニュータウンに店舗を移転、これが現在の有限会社千総の基礎となります。平成14年には四代目の西辻 宏道が代表取締役に就任、平成16年にオリジナルブランド「Atelier confiture」を設立しクラシカルジャムを始め、コンフィチュールシリーズの製造・販売を開始、明治の時代から四代に渡り培った果物への思いを新しいカタチにします。
平成17年には「05 食の博覧会」に出展、少しでも多くの方に私たちのこだわりの味を知って頂きたいという思いを強め、「楽天」での出店販売をスタートさせました。
その後、TV番組など様々なメディアに紹介して頂きまた皆様のご指示を頂く中、さらに商品シリーズを拡大。その一方で日本各地の農園様との連携も強め「生産者の顔が見える」良質な果実を使った、安心で素朴な美味しさを追求した商品づくりを続けています。2023年7月にはカフェ&ショップ併設の本社工場【FRUITS SEASON -NANASOFUTA-】も構え、より美味しいものを皆様へをモットーに、「くだもののある暮らし」を届け続けてまいります。
味乃家は戦後間もないころに初代が女手一つで大阪の地、玉造ではじめた小さなお店(お好み焼き屋)でした。
2代目が食い倒れの街大阪・難波の今の店舗に移し、今では50年以上続くお好み焼き屋です。
故・藤山寛美さんがご贔屓にしてくださったのがもとで、たくさんの芸能人の方々にお越しいただき、人気店としての地位を築きました。現在ではたくさんの世界中の方々がSNSや知人からのご紹介を通じて当店を知って訪れていただいています。
創業当初からお客様の前でお焼するスタイルを続けており、お客様に目で楽しんでいただき、ジュージューとお好み焼きの焼ける音、におい、そして食感など、五感をフルに使って大阪のお好み焼きの醍醐味を存分に楽しんでいただけるサービスを提供しています。
大阪情報雑誌「まっぷる」etc、多数紹介されており『ミシュランガイド京都・大阪』において、2016年版および2017年版で2年連続「ビブグルマン」に選ばれました。
食べログのお好み焼き100名店では5年連続選出していただいています。
2019年に大阪で開催された「G20」でもお好み焼きを実演提供させて頂き河野デジタル大臣にも召し上がっていただきました。
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
わ